私は数年間、不動産会社で働いていたことがあり、不動産の資格をいくつか取得しています。
一番最初に取得したのは宅建。独学で一発で受かりました。
試験結果は
- 自己採点で43点(50点満点中)
- 勉強時間は200時間程度
独学で使用したのは市販のテキストのみ。予備校や通信教育は利用していません。合格に要した勉強時間は約200時間でした。
この記事では、
- 使用したテキスト・問題集
- 具体的な勉強の進め方
について解説しています。
独学でも宅建に合格できた
宅建の合格率
宅建の合格率は15~17%とされています。意外と厳しい試験です。
なかなか1回で受からない方も多いようです。
会社の同僚にも何度も試験を受けている方がいました。ただ、一発で合格している方も意外と多いので、効率的に勉強できれば独学でも十分合格できます。
コツコツ点を積み上げれば合格できる
私は宅建に独学で一発合格できましたが、もともと頭が良いかというと、普通です。自分なりに頑張って入った大学は平均レベル。
宅建は、オリジナルのアイディアや新たな発想などが必要とされる資格ではありません。とにかくコツコツと知識を積み上げれば合格できます。
勉強のモチベーションを保つ方法
私は小さい頃から両親に「泥棒や火事にあって身ぐるみ剥がされたとしても、身につけた知識だけは自分のもとに残るんだよ。だから、頑張って学びなさい。」と言われて育ちました。
私が子供の頃、両親は諸事情により借金を背負ってしまいました。
両親は「今まであったお金が一気に無くなってしまったけど、身に着けた知識は無くならない。自分の子供たちにはそれを教えていかなければ。」と思ったそうです。
私も親という立場になった今、確かにその通りだと感じています。
宅建を受ける理由は「業務に必要だから」「入社試験で有利になるから」という場合も多いでしょう。
でも、宅建で学ぶ知識は自分の暮らしを守る上でも助けになったり、役立つものがたくさんあります。
だから、目先の合格だけではなく、宅建を勉強することで「自分の人生にどんな風に役立つのか?」を意識すると勉強のモチベーションも維持しやすいでしょう。

宅建を学んで得た知識は、人生の糧になります。
宅建合格に必要な勉強時間
一般的に、宅建合格に必要な勉強時間は300時間と言われています。
ちなみに、私が宅建合格までに勉強した時間は約200時間。
平均より100時間ほど少ないです。
合格できた理由は
- 初心者でも理解しやすいテキスト
- 効率的な勉強法
だと思っています。
私の勉強法が一つの参考になれば幸いです。
宅建に独学で受かった、おすすめテキスト
テキスト選びの注意点
まず、法律用語になじみがない方にとって、宅建で学ぶ用語は難しく感じると思います。
私は大学の授業で法律について少し触れましたが、ほぼ初心者。
法律用語は堅苦しいし、分かりづらい…そんな印象を持っていました。(それゆえ、大学の講義はほとんど頭に残っていません)
宅建のテキストを選ぶ際、「よくある教科書的なテキストを選んだら、絶対に受からないな…」と思ったので本屋で何種類ものテキストを読み比べて「かみ砕いた表現で解説してくれるテキスト」を探しました。
結局、テキストを読んで難しい言葉だけ頭に詰め込んでも「どういう意味なのか?」を理解していないと、知識として定着しないんです。
定番「らくらく宅建塾」が、とにかく分かりやすい
私が書店で読み比べて、購入したのは「らくらく宅建塾」です。ロングセラーの宅建本です。
難しい用語もかみ砕いた表現で説明があるので、法律初心者の私でもスムーズに理解ができました。また、イラストも多く視覚的に記憶に残りやすいのも良かったです。
- かみ砕いた言葉の説明で分かりやすい
- イラストが多く、視覚的に記憶に残りやすい
- 語呂合わせがのっているので覚えやすい
- 試験に必要な部分が厳選されてる
らくらく宅建塾のデメリット
らくらく宅建塾のデメリットは、私は特に感じていません。
ただ、口コミをチェックすると「語呂合わせで覚える方法」については評価が分かれています。よって、しいて言えば、この部分がデメリットでしょう。
私は覚えづらい部分は「まずは、語呂合わせでも覚えちゃった方が良い」と考えています。
語呂合わせでも何でも、まずは覚えることで少しずつ知識は身につきます。なかなか覚えられずに苦戦しているよりは、まずは覚えやすい方法で覚えちゃった方が勉強が進みますよね。
余談ですが、高校のときに覚えた化学の元素記号の語呂合わせ歌、いまだに覚えています。あの歌が無かったら、こんなに記憶には定着しなかったはずなので、覚えるきっかけとして「語呂合わせ」もうまく使うと効率的に勉強できます。
使った教材は、テキスト1冊と問題集4冊
最初は「らくらく宅建塾」のテキストのみ購入したのですが、実際に勉強を進めてみたところ、思った以上にスムーズに進んだので問題集も同シリーズで揃えました。
問題集として用意したのは
- 過去問3冊
- 予想問題1冊
です。
基本のテキストを含め、合計5冊を繰り返し勉強しました。
▽過去問3冊(分野別に分かれています)
らくらく宅建塾 過去問
見開き2ページで問題演習+回答確認ができる
らくらく宅建塾の過去問は、
- 左側のページ:問題
- 右側のページ:解答と解説
という構成になっています。
これが、とても使いやすいのです。
問題を解いて、すぐに隣のページで答えが確認できるのでスムーズ。
らくらく宅建塾の問題集は1冊あたりのボリュームが多いです。
最初は「こんなに厚い過去問を3冊も解くなんて…」とひるんでしまいましたが、見開き2ページで1問を解いていくスタイルゆえ「この2ページだけ解いてみよう」と頑張れました。
ちょっとしたことでが、勉強のしやすい構成は大切です。
解説が詳しく、分かりやすい
テキスト同様、宅建初心者に分かりやすいかみ砕いた表現になっているので理解しやすいです。
総仕上げには「ズバ予想宅建塾の問題集」
私が総仕上げに取り組んだのが、ズバ予想宅建塾の問題集です。
ただ、これは必須ではないと思ってます。
まずは過去問をしっかり解けるようになってから挑戦するのが、おすすめ。
過去問3冊だけでも、かなりのボリュームです。
宅建に独学で受かった具体的な勉強方法
私が宅建に独学で合格した勉強方法を紹介したいと思います。

約200時間の勉強時間で取り組んだ内容です。
テキストをざっと読みこむ(5~7割理解できればOK)
まずは、テキストをざっと読んでいきます。
1度で覚えようとせずに「まずは、全体に目を通してみよう」という感じで読み進めました。すると、
- ここは理解しやすいな
- ここは、少し難しいな
- ここは、すごく難しい…
という部分が分かります。
その後、勉強を進めていく上で時間配分をどうすればよいのかが、ざっと把握できます。
過去問をどんどん解いていく
テキストをざっと読んで何となく理解できたら、過去問を解いていきます。
テキストを完璧に理解してからと思っていると、なかなか前に進みません。分からない部分があっても、問題ないので、まずは問題を解いていきましょう。
過去問で生じた疑問点は、テキストで再確認する
過去問で出てきた疑問点は、テキストの該当ページを読み込んで解決していきます。
面倒でも、この作業を1つ1つ繰り返すのが超重要。
実際に問題を解いていくことで、
- 「これについては、こういう問われ方をするんだな」
- 「AとBは関連付けて覚えると良さそう!」
- 「表現の仕方(文言)が変わると迷ってしまうけど、これって〇〇と同じ解釈・意味だよね」
が、分かってきます。
食事に例えるならば、テキストをざっくり読むことで、まずは体に取り込み(=食べる)、問題を解くことで自分のものにしていく(=消化していく)という感じです。
過去問は連続3回正解するまで繰り返す
問題によって
- 1回で解ける簡単な問題
- 何回も間違えてしまう問題
があります。
私は「権利関係」は比較的すんなりと習得できましたが「法令上の制限」は何度も間違えてしましました。
そこで私は、すべての問題を連続3回正解できるまで繰り返しました。
「3回連続で」というところがミソです。
解けたり、間違えたり…ではダメです。
3回連続して解けるようになっていれば、きちんと理解できたといっても過言ではないでしょう。

私は連続3回正解するために、1問あたり7~8回くらい解きました。
理解度をチェックするために過去問のページの端には
- 勉強した日付
- 〇か×(正解・不正解)
をメモしました。
〇が3回続いたら、その問題は完了です。
まとめノートは作らずにテキストに書き込んでいく
過去問を進めていくと
- テキストにしか載っていないこと
- 問題集にしか載っていないこと
が出てきます。
らくらく宅建塾のテキストは「ラクして宅建に受かるためのテキスト」です。試験で出る超重要な内容に絞られています。
それゆえ、問題集には載っているのにテキストには載っていない内容もあります。
これらについては、テキストの該当ページにどんどん書き込んで「自分だけのテキスト」を作り上げていきました。
人によっては「まとめノート」を作るのが得意な方もいらっしゃると思います。
私は「きれいにまとめること」に熱中して覚えるのが疎かになってしまう性格なので、テキストに追記する方法で進めました。
ご自身のやりやすい方法で、取り組んでみてください。
まとめ
独学で合格するために超重要なのは「自分が分かりやすいテキスト」を選ぶこと。
まずは、書店で色々と見比べて、実際にテキストを眺めてみてください。
同じ単元の内容を読み比べて比較すると、違いが分かりやすいです。
テキストによって、説明の分かりやすさは大きく異なります。(正直、分かりづらいテキストは、小難しく書いてあって本当に分かりづらいです…)
テキスト選びに失敗すると、勉強がかなり苦痛になります…。
迷った方は、「らくらく宅建塾」を試してみてください。
講義形式のかみ砕いた説明は、かなり分かりやすいですよ!勉強するなら、楽しく勉強するのがいいですよね。
以上、宅建に独学で一発合格した勉強方法についてでした。

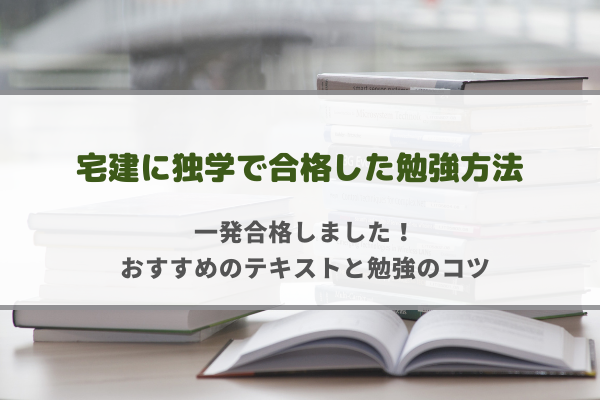
![2025年版 らくらく宅建塾 [基本テキスト] (らくらく宅建塾シリーズ) [ 宅建学院 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4835/9784909084835_1_4.jpg?_ex=128x128)
![2025年版 過去問宅建塾〔1〕 権利関係 (らくらく宅建塾シリーズ) [ 宅建学院 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4866/9784909084866_1_4.jpg?_ex=128x128)
![2025年版 過去問宅建塾〔2〕 宅建業法 (らくらく宅建塾シリーズ) [ 宅建学院 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4873/9784909084873_1_2.jpg?_ex=128x128)
![2025年版 過去問宅建塾〔3〕 法令上の制限 その他の分野 (らくらく宅建塾シリーズ) [ 宅建学院 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4880/9784909084880_1_3.jpg?_ex=128x128)
![2024年版 ズバ予想宅建塾 [直前模試編] (らくらく宅建塾シリーズ) [ 宅建学院 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/4804/9784909084804_1_2.jpg?_ex=128x128)

