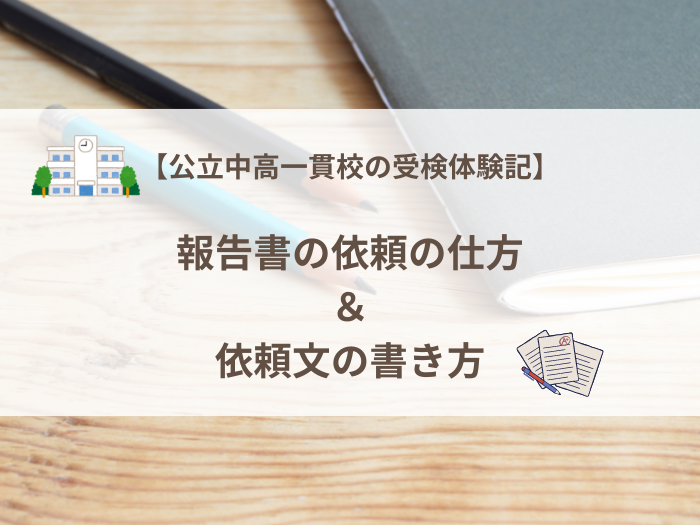公立中高一貫校の受検の際には「報告書」が必要になり、小学校の先生に記入をお願いすることになります。
- どうやって依頼すればいいの?
- お願いするにあたり、依頼書は必要なの?
と悩みました。
ネットで調べてみると「依頼文書は必要ない」という意見が多いです。かしこまりすぎだという意見から。伝えたいことは付箋を貼ればOK!という意見が大半でした。
そこで、私も最初は必要事項を付箋に書いてお願いするという方法で準備し始めたのですが、途中で「うーん…」と思う部分があり、最終的には付箋ではなく、きちんと依頼の文書を用意しました。
ちなみに、我が家の子供は公立中高一貫校のみ受検しましたが、私立を併願する場合にも学校によっては報告書(私立の場合は「調査書」と呼ぶことが多い)が必要なこともあります。その場合についても、参考になるかと思います。
我が家の子供たちは、報告書が必要な公立中高一貫校を受検して、二人とも合格。実体験をもとに、報告書の依頼の仕方や、依頼文の書き方をまとめました。
公立中高一貫校受検の報告書(調査書)の依頼の流れ
受検する予定があるなら、早めに先生に伝えておく
まず、受検(受験)する予定があるなら、早めに先生に伝えておいた方が良いです。
先生は、報告書の記入のための時間を確保する必要がありますし、クラスに受検予定の生徒さんが多ければ、それだけ先生の手間が増えてしまいます。
実際に報告書の準備をお願いするのは秋以降になりますが、先生としても先の予定を把握できていた方が良いはずなので受検を決めたら、早い段階で伝えましょう。
また、公立中高一貫校に加えて私立も併願するようであれば、更にお手間をかけることになります。早い段階で私立を何校受けるのか目処が立っていない場合も「受ける可能性がある」ということを伝えておくのがベター。ギリギリになって伝えるより、先生の負担も少なく済みます。
ちなみに、我が家の子供たちの場合は、夏休み前の面談(7月)で6年生全員に受検(受験)の有無の確認がありました。それなりに受検するお子さんが多いようで、学校側としても事前に大方の人数を把握しておきたかったようです。
事務的に先生の方から「すべてのご家庭に質問しているのですが、受検はされますか?」と質問があったので、ある意味、伝えやすかったです。
我が家の場合は、公立中高一貫校1校しか受検は考えていなかったので、その旨も伝えておきました。(絶対に地元の中学に行きたくないという考えはなく、ダメだったら友達がたくさんいる地元中学で学ばせたいと思っていました。)
▽受検しようと思った理由
▽子供の気持ち、親の気持ち
報告書(調査書)の入手の仕方
報告書の情報は受検校のホームページをまめにチェックするのが基本です。多くの学校が秋には報告書について情報をアップします。
今年度の情報がアップされる前でも、前年度の情報が残っている場合が多いです。その場合は、前年度の分に目を通しておけば大体の流れが分かります。もちろん、年によって必要な書類や時期が変わる可能性があるので最新情報のチェックも念入りにしましょう。
報告書の情報に限らず、学校説明会の情報なども公式ホームページに掲載する学校が多いです。受検する予定があるならマメにホームページの確認をした方がいいです。学校説明会や見学会に参加することで、親も子供も、受検が「自分のこと」として身近に感じるし、志望校との相性も見極められます。
ちなみに、私は2~3日ごとにチェックしていました。そんなに頻繁に情報は更新されませんが、情報収集やモチベーションを上げるという意味でも、マメにチェックするのは良いと感じました。
報告書(調査書)の依頼はいつする?まずは先生に相談するのが大切
志望校の情報を見て、報告書が必要だと確定したら早めに先生に依頼しましょう。でも「早めってどのくらい?」と思いますよね…。
ネットで調べてみると
- 1か月くらい前
- 報告書に記載する成績がでるのは12月になってからなので、12月に入ってから
という意見が多かったです。
一般的には、そのくらいなのかもしれません。でも、あくまでネットの情報です。一番、確実なのは担任の先生に聞いてみることです。
我が家の場合、子供の担任の先生との夏休み前の面談では、先生から「必要な書類がある場合は、早めにお願いします」とお話がありました。その時点で、具体的にどのくらい前が良いのか質問しておけば良かったのですが、その時点で、私もそこまで詳しいことを考えてなかったので聞かず…。
私は、報告書の詳細が分かったら、早めに依頼文書を作成。それが完成次第、先生に電話で時期を相談してみました。すると、「できるだけ早くいただきたい」というお返事。
かなりハイペースではありますが、先生が、その日の夕方にお時間とれるということなので、即日お持ちしました。(私もちょうどその日に予定がなくて、すぐ対応できたため。)
ネットの情報よりだいぶ早く渡すことになったので、先生に直接質問してみて良かったです。
もちろん、担任の先生によって希望する時期は違うでしょうし、12月を希望する先生も多いのかもしれません。個々によって異なるでしょうし、まずは相談してみると良いと思います。
報告書(調査書)の依頼の仕方
報告書は子供に持たせるのではなく、放課後に、直接お持ちしました。
その際、下校後の子供も一緒に連れていきました。親だけで行くのが普通なのか、子供も一緒に行くのが普通なのか迷いました。
でも、受検するのは子供だし、子供も一緒にお願いしたほうが誠意が伝わるかなぁ…、と思ったので連れて行きました。
子供も一緒に来たのを見て、先生が「わざわざ来てくれたの~!ありがとう!頑張ってね!」とにっこり。励ましてもらって、子供も身が引き締まったようでした。一緒にお願いに行って良かったです。
もちろん、お子さんを連れて行くのが難しい場合は、親だけでも問題ないと思います。きちんと誠意が伝わる渡し方でお願いすれば大丈夫です。
報告書(調査書)が複数必要な場合はまとめてお願いする
公立中高一貫校以外に、私立も併願する場合、複数の報告書を依頼するケースもあります。先生に何度も時間をとっていただくのは、お手間をかけてしまうので、できるだけまとめると良いでしょう。
ただ、タイミングによっては、全部まとめてお渡しするのが難しい場合もあると思います。そのような場合は、まずは先生に相談してみて、今後、どのくらいの時期にお願いする予定なのかを伝えておけば良いと思います。
後になって、急に頼まれたら先生も大変でしょうし、事前にスケジュール感が把握できていた方が対応しやすいですしね。
お礼の品物は必要なし
報告書の作成にあたり、菓子折りなどのお礼の品物は必要ありません。先生も困ってしまうでしょうし、受け取ってもらえないと思います。
我が家の場合も、何もお礼は渡していません。
気を付けたのは
- 先生に早めに伝えておくこと・依頼すること
- 先生が作業しやすいように、依頼文書を作成したこと
- お礼をきちんと伝えること
ちなみに、親がPTAの役員をしていると報告書の内容が良くなる…等の噂もありますよね。我が家の場合は、親はPTAの役員など目立った活動はしていません。それでも、子供2人は公立中高一貫校に受かっています。
※私立の場合は、親の活動がどのくらい合否に影響するのか、私には分かりません。あくまで、我が家の子供が受検した公立中高一貫校においての体験談です。
公立中高一貫校の報告書作成の依頼文の書き方
ネットでよく見かけたのは、「依頼文書は改まりすぎだから、伝えたいことは付箋に書いて書類に貼っておけばOK」という意見。最初は私も付箋スタイルで用意してみました。でも、付箋が4枚くらいになってくると、なんだかゴチャゴチャしている印象。
先生に書類を渡すときに、口頭でもそれを補足できるなら問題ないかもしれないけど、そこまで時間が取れないかもしれないですしね。付箋のみで伝えるって、ちょっと気が引けるなぁ…と思って夫に相談。
すると、「心配なら、お手紙を用意すればいいじゃん!その方が丁寧なんだしさ。」との返答。
確かに!
時間を割いて作っていただくんだし、丁寧にお願いしようと思いお手紙を準備することにしました。
あくまでも、私の考えです。普通がどうなのかは分かりません。ちなみに、同じ学年の他の保護者の方がどのように依頼していたのかは分かりません。ママ友間でも、受検の話題って難しいですよね(汗)
私が書いた依頼文の例
一番気になるのは「先生への依頼文はどういう感じで書けばよいの?」だと思います。
要点は把握していも、具体的に文章に落とし込むのって、悩むもの。ネットで探しても、例文はほとんど見つかりませんでした。
私は「簡潔に、かつ漏れなく伝える」を意識して、文書を作りました。でも、先生が初見でも理解しやすい内容にまとめようと思ったら、それなりの文章量になりA4一枚がびっしりになりました。
私の場合は、↓のような感じで作成しました。
〇〇小学校
6年〇組 〇〇先生
お世話になっております。いつもご指導頂き、ありがとうございます。
以前、個人面談でお伝えいたしましたが中学受検を予定しております。お手数ではございますが、〇〇学校へ提出する書類の作成をお願いいたします。提出用書類を同封いたしましたので、御多忙のところ大変恐縮ではございますが何卒宜しくお願いいたします。
∙受検校:〇〇学校
∙作成頂きたい書類:〇〇
∙書類の受け取り希望日:〇〇
◇作成いただきたい書類
※ここに作成をお願いする書類や、作成いただく上での要点を記入
◇出願期間と受け渡しについて
出願期間が〇月〇日~◇月◇日のため、作成頂いた書類を□□(※日付を入れる)までにいただきたく、恐れ入りますが宜しくお願いいたします。
受け渡し日時をご連絡頂けましたら、学校へ受け取りに伺います。
以上です。ご不明点等ございましたら、ご連絡いただければ幸いです。お忙しいところお手数をお掛けいたしますが、何卒宜しくお願いいたします。
親の名前と電話番号
必要最低限ですが、要点はまとまっていると思います。
- あいさつ文
- 作成していただきたい書類
- 作成いただく上での注意点など
- 受け渡しについて
- 質問等があった場合の当方の連絡先
を入れました。
先生はもちろん、こちらの連絡先はご存じですが、このお手紙一枚あれば報告書作成については足りるようにしたかったので、念のため連絡先も入れておきました。
我が家の場合、受検に関しては、夫ではなく私が担当していたので、私の携帯番号を記載しました。
大切な部分にマーカーをしておく
依頼文の特に大切な部分には、マーカーを引いておきました。
封筒は小学校側で用意してもらえた
受検校から「報告書は封筒に入れて厳封する」よう指示がありましたが、「封筒は誰が用意するの?」と気になりました。
書類の作成は先生にしてもらうけど、封筒まで用意してもらっていいのかな?と。
そこで、報告書を依頼する際に指定サイズの封筒(茶封筒)も持参。先生に封筒も念のためお持ちした旨伝えると「小学校で用意した封筒を使うので、必要ありませんよ」とのお返事。
子供の通う学校の場合は、学校側で用意してもらえました。
ネットで検索した際は、少数派ですが自分で用意して渡したという体験談がありました。大半は学校側で用意してもらえるようです。
受け渡し方法や期日を確認・相談しておく
先生へのお手紙にも報告書をいつ受け取りたいか記載しましたが、口頭でも相談・確認しました。
子供たちの小学校の場合は、担任の先生が報告書を作成後、校長先生に確認を取ってから渡してもらえる流れでした。
12月までの成績が関係するので、その評価が終わってから。そして、校長先生の確認を得てからとなると、スケジュールがある程度、見えてきます。
ただ、校長先生が体調不良で休んでしまったり、出張に行ってしまったりすると確認できる日が遅くなってしまうこともあるとか。
報告書の作成には、担任の先生以外の方の予定も関わってくるケースも多いでしょうし、事前にどんな流れ(日程)で受け取れるのか確認しておくと安心です。
以上、報告書の先生への依頼方法についての体験談でした。
【塾なし家庭学習で勉強しました】
▽Z会の通信教育をメインに、市販の教材を買い足して勉強しました。
▽受検対策に役立った問題集リストと感想(まとめ)